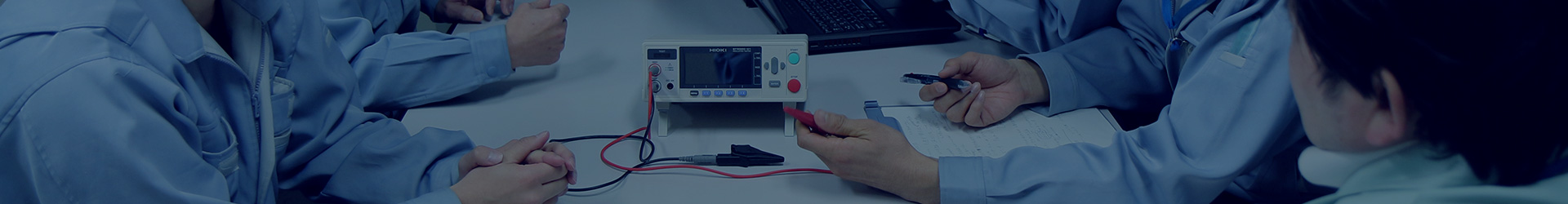LCRメータによるモーターのワニス含浸状態の試験
低い周波数でtanδを測定することで、モーターのワニス含浸状態の違いが明確に分かります。
モーターは電気エネルギーを機械エネルギーへ変換する装置として、EVや電車をはじめとする輸送機器産業、暖房換気空調機器(HVAC機器)産業など幅広く使用されています。モーターの電気絶縁性は、安全性、性能、耐久性にかかわるため、製造工程やメンテナンスおよび修理の際に検査されます。
モーターの主要構成部品であるステータは、鉄心コアに絶縁線を巻くことで作られます。その後、ワニス含浸処理*をすることでコイル内部や絶縁紙の絶縁機能を補強し、さらにコイル内部にできてしまう隙間をワニスで埋めることで、絶縁劣化につながる湿気やほこりの侵入を防ぎます。
* ワニス含浸処理は、絶縁材料であるワニスが入ったタンクに浸す「滴下含浸」と、真空状態にしてワニスを充填させる「真空含浸」のいずれかの方法で行われます。
◤ 含浸状態を、より正確に把握するには
モーターのワニスの含浸状態の検査では、一般的に誘電正接計(tanδ計)が用いられます。誘電正接 tanδとは、電気絶縁材料の状態を数値で表す指標です。絶縁体(コイルと接地間)に交流電圧を印加すると、誘電損(または誘電損失)が起こります。tanδは、この誘電損の度合いです。
モーターの誘電正接計測は、50 Hzもしくは60 Hzの比較的高い電圧を印加して行われます。誘電正接は tanδ=1/2πfCRp で表せるため、周波数 f が低くなるとtanδは大きくなります。つまり50 Hzもしくは60 Hzより低い周波数で測定できれば含浸状態の違いが大きくなり、より正確に把握できることが期待できます。
◤ LCRメータを使用した解決策
真空含浸の良品と含浸度が足りなかった不良品のステータサンプルをそれぞれ用意し、LCRメータでコイル-コア間のtanδを測定しました。その様子と実測データを以下に示します。特に外乱ノイズの影響を受けやすい高インピーダンス測定のため、シールドボックスでモーターを囲み、シールドボックスとLCRメータのGUARD端子を接続します。また、測定時はシールドボックスの6面すべてを閉じて行うなどのノイズ対策が必要です。
◤ 実測データ
LCRメータ設定: 測定周波数=10Hz, 測定信号 CV=5.0V, 平均化回数=50回
誘電正接(tanδ)と抵抗値(絶縁抵抗Rp)とIrに大きく違いが出ました。良品(Sufficient)の方がIrとtanδともに大きくなりました。これはワニスの量が多くなり、誘電率の低い空気が減ると電極間(コイルとコア、相と相)の抵抗値が下がるとともにIrが増え、Irが増えたことによりtanδが大きくなったことを指します。
◤ 考察
・ワニスがない状態のモデル図と等価回路 (Fig.10) ではコアとコイルが電極となり、空気と絶縁紙で絶縁されています。
・空気と絶縁紙による合成静電容量をCaとします。
・ワニスがある状態 (Fig.11) ではワニスも絶縁物として加わり空気の量が減るため、静電容量が小さくなったCaとワニスの静電容量Cvの合成静電容量になります。
・静電容量は C = ε*S/d (F) で電極面積Sと電極距離dが変わらないとすると誘電率εで決まります。
・空気の誘電率は1です。ワニスの誘電率は最低でも2.8です。従って絶縁物の誘電率が上がったため、静電容量が上がりtanδも上がったものと推測できます。
・電極面積Sが大きいUVW-GではtanδやIrの違いは少ないですが、Rpは明確に違う結果を得たことが分かります。
関連製品一覧