資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
アプリケーション・用途
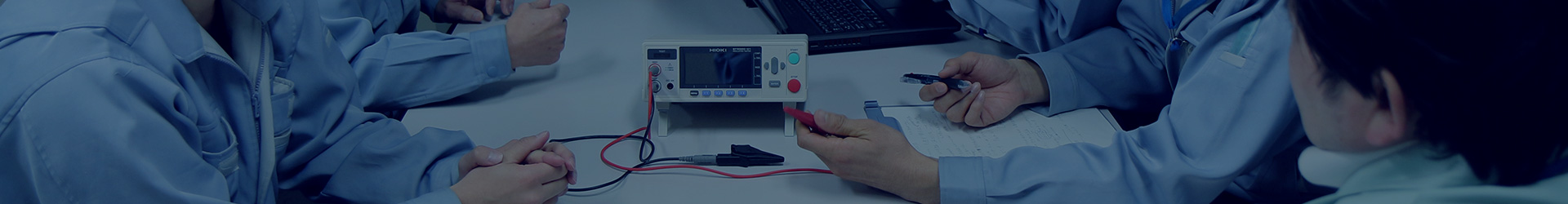
レアショート試験は、インパルス巻線試験とも呼ばれ、トランスやモーターといったさまざまな機器の巻線を検査するのに導入されています。この試験では、巻線にインパルス電圧を印加し、その応答波形を測定します。そして、試験対象品の応答波形を良品(マスター波形)と比較し、良品か不良品かを判定します。
しかし、従来の波形比較法にはいくつか課題があります。まず、応答波形の違いが分かりにくいため、明確な判断が難しいことがあります。また、波形の差が巻線の特性と直接結びつかないため、故障原因を特定するのが難しいという問題も抱えています。さらに、マスター波形との相対比較となるため、判定基準の設定や更新が面倒になることも少なくありません。
このアプリケーションノートでは、これらの課題を解決する新しいアプローチを提案します。このアプローチでは、レアショート試験で得られた波形から等価回路定数(L値とR値)を推定し、これらの数値を用いて合否を判定するという方法です。この手法は、従来の波形比較法に比べて、より客観的で効率的な巻線・コイル評価を可能にします。
レアショート試験における従来の波形判定法が具体的にどのような課題を抱えているのか、詳しく見ていきましょう。
図1 相間の応答波形比較
図1は良品の三相モーターの各相間にインパルスを印加したときの応答波形です。良品のモーターにおいては、すべての波形がきれいに重なって一本の線のようになるのが理想です。しかし、ばらつきによって配線の応答波形が異なることがよくあります(図1の赤丸参照)。
従って、波形を比較して合否を判定するには、複数の良品の応答波形を観測し、統計的にばらつきの範囲を求め、その範囲から逸脱しているかどうかを判定する必要があります。
図2 ワンターンショート(0.5 Ω)の応答波形
図2は、あるステーターの巻線ワンターン間を0.5 Ωの抵抗器でショートする前後の応答波形を、弊社のST4030Aで観測したものです。黄色の波形がショート前、青色の波形がショート後で表示されています。
青色波形は意図的にレアショートを起こした明らかな不良サンプルの応答波形ですが、ショート前の波形と比較してもその差はわずかであることがわかります。この程度の差では、図1の良品のばらつきの範囲とあまり変わらず、波形による比較では良否判定が困難です。
このように、波形比較(波形に囲まれた面積の比較を含む)には本質的な限界があり、信頼性の高い欠陥検出には不十分な場合があります。
波形比較の限界を克服するために、このアプリケーションノートでは数値による評価方法を提案します。
図3a 良品: 図2の黄色の波形
図3b 不良品: 図2の青色の波形
図3 図2における良品(黄色の波形)と不良品(青色の波形)のLとRを測定
図3は、それぞれ図2における良品(黄色の波形)と不良品(青色の波形)のLとRを測定したものです。これを見ると、あきらかに不良品の数値が良品のものと異なっているのが分かります。このように試験品の回路定数を推定し比較することで、波形を比較するよりも良否判定がしやすくなります。
次に、L/R値の算出方法とこれらの値を使用した際のメリットについて説明します。
図4 測定等価回路
このアプリケーションで使用している試験器と測定対象(DUT)の測定等価回路を図4に示します。測定器(ここではST4030Aとします)側のCに充電された電圧をスイッチによりDUTに印加し、その時の電圧応答波形を取得します。
図5 応答波形例
図5は、100 Vのインパルス電圧をDUTに印加した際の応答波形です。この応答波形の最初のピークに続く減衰部分を利用し、図で想定した等価回路の微分方程式に当てはめます。そして、最小二乗法を用いてL値とR値を推定します。その後、カーブフィッティングにより適切な定数を求めます。
測定対象によっては振動しない波形となる場合がありますが、波形の最初の減衰部分が演算範囲となるため、振動しない波形でもL値とR値を算出できます。
ここで算出されるL値とR値は、LCRメーターで測定される値とは異なる点にご注意ください。これは、このアプリケーションで使用している等価回路とDUTの実際の特性との差や、LCRメーターとインパルス巻線試験器における電圧の大きさや印加方法の違いなどが原因で、LCRメーターで測定する値との差が生じるためです。
ただし、DUTの特性が想定等価回路に近く、LCRメーターの測定周波数がインパルス波形の最初の周期に近い場合は、値の違いは小さくなります。
トランスやモーターなどの巻線検査に用いられるレアショート試験(インパルス巻線試験)は、これまで波形比較により良品と不良品を判定してきました。しかしこの手法には、インパルス波形から等価回路定数を正確に抽出できないという根本的な課題がありました。そのため、既知の良品波形との比較に頼らざるを得ず、違い良性なのか不良なのかの判断が難しく、欠陥原因の特定も困難でした。
弊社のST4030A専用ソフトウェアは、この課題を解決します。インパルス応答波形から直接LとRの回路定数を抽出することを可能にし、以下の点で大きなメリットをもたらします。
L/R推定値による詳細な評価方法やそのほか関連試験について、ぜひお気軽にお問い合わせください。
特定のアプリケーションに関するデモンストレーションやご相談は、お問い合わせフォームから弊社までご連絡ください。
コイル用L値R値デモアプリケーションは、こちらからダウンロードできます。