資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
アプリケーション・用途
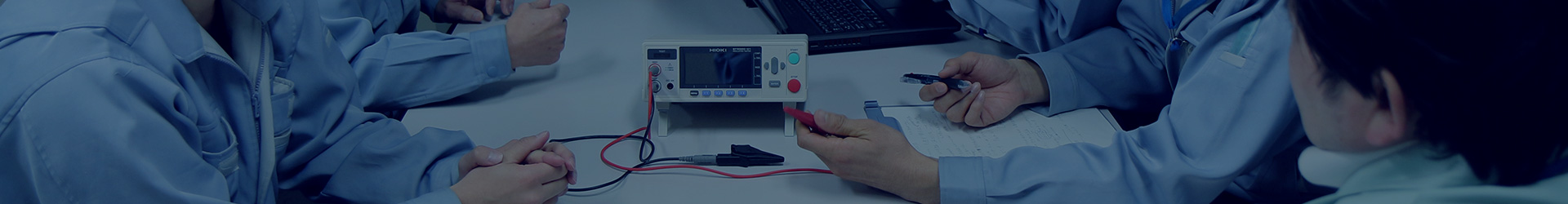
1現状把握
工場全体、各部署フロア、個別機器に至る環境 / 生産エネルギーの関係を把握しましょう。電力ライン系統ごとの使用機器の種類、数量などを調査します。そして現状の電力使用状況や生産 / 環境エネルギーの割合などを、測定器を用いて調査してみましょう。各電力ラインや使用機器ごとの電圧、電流、有効電力、有効電力量の基本測定に加え、無効電力、最大電力、力率、デマンド電力、照度、温度、圧力、騒音などの各種エネルギーをできるだけ同時に測定できれば、解析に役立つデータが得られます。
電力の測定方法としては、30 分デマンド測定を基準に、測定期間を 1 日・1 週間・1 ヶ月単位で測定し、なるべくデータの平均化を図り傾向を把握しましょう。また、測定時には測定対象にあわせて、使用状況や環境条件、運営方法なども調査しましょう。一例として照明機器では、使用状況として...消費電力量 / 点灯数量 / 点灯時間など、環境条件として...機器の照度と照度分布 / 温度と温度分布など、運営調査として...点灯基準 / 点灯者 / 点灯時間の管理などを調査します。
2分布
測定された各データをグラフ化し、時間帯ごとの機器の特徴や運営の特徴を調査します。(力率、負荷率、需要率、デマンドグラフや電力原単位など)
3改善のポイントの抽出
電気理論、設備機器に関する知識をもとに、最大電力の低減や効率的な運転方法や不要運転などの原因を調査します。分析グラフから最大電力の削減、稼働率が低下している時間帯での削減、負荷平準化のための機器使用数量の削減、使用時間の削減、同期運転の防止、機器の入れ替えなどあらゆる角度から検討してみます。
4改善計画
データをもとに、機器の削減方法、作業時間の変更などの手順を決めて運用マニュアルを作成します。機器の新規導入に際しては、機器の償却、ランニングコストについて試算をおこない導入の適正性を検討してみましょう。
5改善の実施・検証
運用マニュアルに従って実施してみます。現状把握でおこなった測定と同じ方法・条件で測定をおこない、改善前と同様にデータのグラフ化をおこないます。
6効果の確認・まとめ
改善前と改善後データを同一時間軸で重ね合わせて確認してみましょう。改善されたコストの算出、機器ごとの改善率、改善時間帯などをまとめてみます。