資料ダウンロード
カタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。
サポート情報
会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。
購入・レンタル
購入・レンタル・見積もりのご案内です。
購入時のご注意事項
アフターサービス
製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。
企業情報
HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。
サステナビリティ
すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。
IR情報
株式情報、財務・経営情報を掲載しています。
採用情報
新卒・キャリア採用についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
アプリケーション・用途
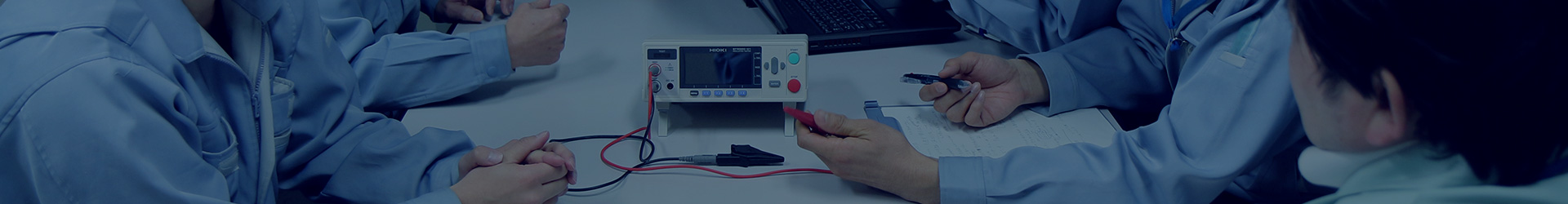
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)の普及に伴い、大電流を扱うシステムが増加しています。バスバーや接合部などの電流経路におけるわずかな抵抗が、システムの効率低下や過剰な発熱を引き起こすリスクに直結します。こうした課題を解決するため、高精度な低抵抗測定が不可欠です。
HIOKIの抵抗計RM3545Aは、1 nΩの分解能で微小な抵抗を正確に測定します。測定対象へのプロービング技術を最適化することで、信頼性の高いデータを提供し、お客様の製品品質の向上をサポートします。この記事では、低抵抗測定の成功の鍵であるプロービングのポイントを、実例を交えて解説します。
HIOKIの抵抗計RMシリーズでは、定電流方式を採用しています。測定対象(DUT)にSOURCE(電流印加ライン)から一定の電流(I)を流し、SENSE(電圧検出ライン)で電圧(V)を検出します。オームの法則(R=V/I)に基づき、抵抗値を算出します。4端子測定(ケルビン測定法)は、電流印加経路と電圧検出経路を分離することで、経路抵抗=配線抵抗+接触抵抗の影響を排除できるため、低抵抗測定において信頼性の高い結果を提供します。「抵抗測定の手引き」の8ページから9ページも併せて参照してください。
ここでは、4端子測定を前提に、プロービングのポイントを詳しく解説します。
図1 4端子測定
低抵抗測定では、プロービングの方法が測定結果に大きく影響します。理想的な電流の流れ(一様な電流密度)と、実測時の電流の流れ(不均一な電流密度)の違いが、測定誤差の主な原因です。
ここでは、チップ抵抗器(面実装抵抗器)と金属丸棒を例に挙げ、理想状態と実測時の測定電流の流れ方と測定値に与える影響について詳しく見ていきましょう。
チップ抵抗器は基板に実装して使用されるため、その仕様値は基板実装状態での抵抗値となります。図2のように、基板実装状態では、抵抗器の抵抗体に電流が一様に流れています。例えば、一様に電流を流している状態で電極両端に生じる電位差(図中の等電位線の数に等しい)を検出してみると、オームの法則により仕様値に近しい抵抗値を測定することができます。
金属丸棒の理論抵抗値Rは、R=抵抗率ρ×長さL/断面積Aで求められます。この理論値は、丸棒内部に一様に電流が流れている場合の抵抗値になります。
図2 電流の流れ方(理想状態)
図3に低抵抗チップ抵抗器、高抵抗チップ抵抗器、金属丸棒を実測した場合の、内部の電流の流れ方を示します。
低抵抗チップ抵抗器や金属丸棒の測定時は、不均一な電流の流れ方をします。一様な基板実装時の電流の流れ方とは異なります。高抵抗チップ抵抗器測定時は、電極-抵抗体間の抵抗値差により、先に電流が拡散します。そのため、基板実装状態と似た一様な電流の流れ方になります。 金属丸棒の測定時は、プロービング箇所から電流が放射状に拡散します。理論値の状態とは異なり、不均一な電流の流れ方をします。
これらの電流の流れ方の違いによって、測定値に影響があります。次項でより詳しく見ていきましょう。
図3 電流の流れ方(プロービング時)
図4のようにプロービングして低抵抗のDUTを測定した場合、部品の角など、ほとんど電流が流れない領域が生じることがあります。前項の理想状態とは電流の流れ方が異なるため、電流の流れていない部分は測定できず、結果として仕様値や理論値と測定値にずれが生じます。
例えばSOURCE付近にSENSEをプロービングした場合は、実測抵抗値は仕様値・理論値よりも高くなります。これは、見かけ上のDUT断面積が小さくなる(ρ×A/LのAが小さくなるイメージ)ためです。ただし、SENSE-SOURCE間距離によっては、この関係が逆になることもあります。
図4 不均一な電流密度
低抵抗のチップ抵抗器を例に考えましょう。
不均一な電流密度である実測時にて、電流密度が高いSOURCE点周りは等電位線の間隔が狭くなります。 仮に、等電位線が1 mV間隔として、SOURCE A - SENSE A間距離がプロービングごとに1 mmずれる場合を考えてみましょう。
図5の通り、SENSE - SOURCE間距離の大小で、同じ1 mmのずれでも電圧変動が異なります。検出電圧が抵抗値に換算されるので、それはそのまま抵抗値の変動となります。 つまり、SENSE - SOURCE距離が大きいほど、プロービングの位置がずれても検出電圧の変化が少なく、そのため抵抗値の変動も抑制されます。その結果、図6の通り測定の繰り返し精度が向上します。
図5 SENSE - SOURCE間距離と検出電圧の変動
図6 SENSE - SOURCE間距離による測定値のばらつき
以下のテクニックを実践することで、測定の精度と再現性を飛躍的に向上させることができます。
一般的にはDUTの幅・厚みの3倍以上SENSE-SOURCE間距離を離すことが理想とされています。この場合、一様な電流の部分を計測することができ、「仕様値・理論値と測定値のずれ」や「プロービングごとの測定値のばらつき」を抑えることができます。
ただし、多くの測定対象は、十分にSENSE-SOURCE間距離を離して測定することは困難です。この場合、理論値や仕様値を測定値と一致させることは非常に困難です。チップ抵抗器の仕様値や金属丸棒の理論抵抗値は、その中を電流が一様に流れる前提の値です。実測状態とは電流の流れ方が異なるので、双方の値は異なります。
このような場合は、良品と不良品の抵抗値を相対的に比較するというアプローチを推奨します。また、SENSE-SOURCE間距離を理想的に確保できない場合でも、プロービングごとの繰り返し精度を向上させるため、可能な限りSENSE-SOURCE間距離を確保することをお勧めします。
測定値を理論値に近づけたい場合、HIOKIでは図7のような6端子計測を提案いたします。これは電流経路を2つ用意し、基板実装状態の電流密度に近づける手法です。
詳細は、HIOKIアプリケーションノート「6端子抵抗測定で、基板実装状態に近いシャント抵抗値を検査」を参照ください。
図7 6端子計測
プロービング位置の再現性を高める治具を使用することで、測定値のばらつきを最小限に抑えます。
低抵抗測定は、プロービングの工夫で精度と信頼性が大きく向上します。RM3545Aと本記事で開設したプロービングのノウハウを活用し、抵抗の品質管理を強化しましょう。
特定のアプリケーションに関するデモンストレーションやご相談は、お問い合わせフォームから弊社までご連絡ください。